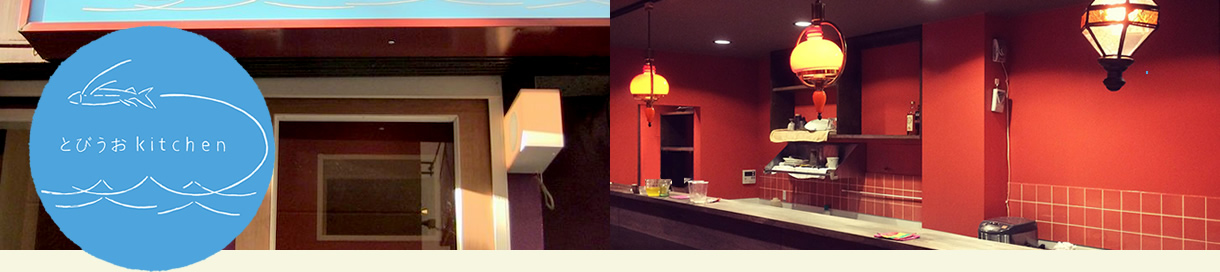「とびうおキッチン」最終イベント『80年代個人映画の記憶』!!
8mmカメラは〝私〟と〝世界〟が対峙するための武器だった…。80年代の個人映画作家たちが記録した、内向する眼差しと言葉の記憶が、30年近くの歳月を超えて蘇る。
『とびうおキッチン』の最後を飾るイベントは、2代目店主・鈴木章浩が独断で選んだ、今、観たい!観せたい‼︎80年代8mmの特集上映!!!
料金:1プロ: 1000円、2プロ : 1700円、3プロ: 2500円(全て1ドリンクつき)
完全予約制!!!(各回定員15名)
予約は下記のメールアドレスに、お名前、参加人数、連絡先、鑑賞プログラム名(A,B,C)をご記入の上、お送りください。席数が限られるため、定員に達し次第締め切らせて頂きます。
予約:tobiuo@asahinet.jp
++++++++++++++++++++++++++++++
自分の映画を撮りたいと思った時、8mmしか選択肢がなかった時代。8mmカメラを手に、自分の存在や表現と格闘した個人映画作家たち。個人の作品であるがゆえに、今では観ることが出来ないものも多いが、その多様で豊かな映画の世界が存在したことは、忘れてはならない。表の映画史に浮かんで来ることのない、埋もれた沢山の美しい映画たちを、私は憶えている。
今回上映するのは、私の映画的記憶の中で、忘れることの出来ない作家と作品たち。今後上映される機会があるかどうか分からない、貴重な作品を特にラインナップした。作家の方々も、遠方よりはるばる来場される。これは回顧ではなく、新たな発見と出会いの場である。
上映作品(全て8mm作品)
Aプロ:13:00-【浜松個人映画の80年代】
『夏が過ぎれば』40分 稲垣宏行
『双子座(Gemini)』10分 稲垣宏行
『蝉ヌード』1987年 20分 袴田浩之
『Bye-Byeメール』1986年 4分 上原昌子
Bプロ:14:45-【80年代の後の風景】
『がむぜ4』(オムニバス)1990年 17分
山崎幹夫、酒井知彦、石井秀人、小口詩子、鈴木章浩
『風わたり』1991年 30分 石井秀人
Cプロ:16:15-【日常と奇跡】
『デッド・エンドレス』1983年 12分 竹平時夫
『過去形という魚』1985年 54分 鈴木章浩
来場予定:袴田浩之氏、石井秀人氏、竹平時夫氏
*上映終了後、18:00 過ぎより出品作家を交えての交流会「とびうおキッチンさよなら会」を開催します。21:30位までダラダラと交流しましょう。詳細は追ってお知らせします。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
▪️鈴木章浩による個人的で長いプログラム解説
Aプロ解説
80年代の中頃まで、浜松に「イメージ・マーケット」という自主映画団体があった。メンバーは木造のアパートの2階にあった事務所に集まっては上映会の企画をしたり、撮影してきたラッシュや作品を見せ合ったりしていて、それが終わると大抵は飲み会になった。事務所の冷蔵庫には常にビールなどが備蓄されていた印象がある。60年代から8mmを作っていたベテランから、映画を撮りたい高校生まで様々な人たちが出入りしていたが、バブルの恩恵を受けて踊っているような人間は一人もいなかった。
美術畑出身の作家たちが身の回りを撮った日記映画 を撮っていた中、稲垣宏行は異色の劇映画 『夏が過ぎれば』を作った。メモ程度のシナリオしかなく、最小限のスタッフと出演者のみで作られたこの映画 には、凝った演出も素晴らしい演技もなく、衝撃的な物語も存在しない。男女の恋愛物語の断片が、長回しによって風景のように淡々と映し出されているだけだ。しかし、そこには映画的としか言いようのない時間が流れ、作者の言葉にならない孤独や痛みの感情が観る者の胸に沁みてくるのだった。個人映画と劇映画の融合という意味で、今ならガレルやユスターシュを思い出すところだが、当時の我々には観ることは叶わなかった。今回、ほとんど公開されることのなかったこの傑作が上映出来るのはこの上ない喜びだ。『双子座』は、私が音楽を付けさせてもらった実験映画的な手法の作品。二つのギターのうち、アルペジオを失敗している方が私だ。
80年代なかば、「イメージ・マーケット」は「シネマ・ヴァリエ」と名称を変え、所属メンバーも作られる作品の傾向も変わった。「シネマ・ヴァリエテ」の代名詞となった〝ダイレクト・シネマ〟は、日常の閉塞感をぶち壊したいという衝動を映画にしようとしていたが、袴田浩之の家庭内暴力映画『蝉ヌード』は、その思想を最も直接的に具現化し、〝ダイレク・トシネマ〟のイメージを定着させた問題作だ。袴田は〝壁を壊す〟という言葉を比喩的に表現するのではなく、実際に部屋の壁を壊すという現実の行為としてダイレクトに提示した。そこには日常に埋没する旧世代の日記映画への苛立ちと、映画という手段によってくだらない日常を破壊したいという願望が、表現以前に行為として記録されている。8mmカメラは行動を起こすのための武器となったのだ。一方、「イメージ・マーケット」時代からのメンバー上原昌子は、私的な日記映画を作り続け『Bye-Bye,メール』では、震えるカメラとナレーションで、撮影している自分とその行為を見つめている。わずか4カットしかないこの詩的な短編は、PFFアワード1987年に入選した。
この企画の実現にあたり、多大な協力をいただいた袴田浩之氏に感謝する。
Bプロ解説
80年代終わり、8mm映画界の巨匠・山崎幹夫さんの主催した映像ワークショップが何回か開かれ、多くの映像作家たちが特定のコンセプトに基づいた3分間のフィルムをその場で撮影した。私もそのうち2つに参加させてもらったが、その1つが『がむぜ4』だった。渡された地図の経路を辿って、あらかじめつけられた目印を写し込みながら3分間の撮影をするというコンセプトだったが、私は当時2歳だった息子の映像を事前に撮影したフィルムを使った。二つの時間を重ねたかったのだ。小口詩子がリカちゃん人形を持って来たり、参加した作家がそれぞれ独自の演出を仕込んで撮影に臨んだので、各自の個性の違いが楽しめると思う。今回上映されるのは、9人の参加者のうち5人の作品を編集した短縮版。中でも、石井秀人の作品の〝8ミリ映画の女神さまが微笑んでいる〟と評された映像の美しさには注目して欲しい。山崎さんのワークショップには、園子温、平野勝之、佐々木浩久、鈴木卓爾、藤原章、大川戸洋介なども参加していて、今にして思えば、結構豪華な顔ぶれのワークショップだった。
石井秀人の『風わたり』は、石井作品の一つの到達点とも言える傑作だ。『家、回帰』という傑作をいきなり作ってしまった石井は、家族や老いや死というテーマ、そして映画を撮るということ自体と格闘しながら、作品を作り続けてきた。多作な作家ではないが、その光に対する感覚や、対象を見つめる視線は作品ごとに鋭さを増し、ここに至って8mm個人映画という表現の一つの頂点を極めたといっても過言ではないだろう。個人的に最も再見したかったのは、彼の映画の中でも異色の『以北より』だったが、フィルムの状態が悪く切れる心配があるということで上映を諦めた。大雪原の中にカメラを立て、文字通りすべてを捨てて裸になり、映画と対峙しようともがく石井の姿が強烈な印象を残すこの作品は、その破綻した感じも含めて、もう一度観てみたかったし、観せたかった。それにしてもフィルムが心配だ。
Cプロ解説
何かに8mmカメラを向けると、時々奇跡が起こることがある。竹平時夫の『デッド・エンドレス』のオープニングはまさにそんな奇跡のショットだ。奇跡と出会うのも才能がなければ出来ない。そうした奇跡と出会うために、当時、個人映画作家は8mmカメラを持って町をうろうろしていた。彼がどんな手段を使ってこの奇跡を起こしたかは分からないが、そのショットが撮れた日に「すごいのが撮れたんだよ」と言っていたのは覚えている。竹平時夫と私はイメージフォーラム映像研究所の同期だったので、撮影や仕上げを手伝ったりした。『デッド・エンドレス』は日記映画的に作られた作品だったので、シナリオというものがなく、良いショットは撮れていても、それをどう作品化するかで悩んでいるようだった。その苦悩のプロセスも作品の中に取り込みながら、試行錯誤を続ける中、たどり着いたのが個人映画史上に残る衝撃のラストだった。その撮影に付き合った私は、その決意に驚きを隠せなかった。ここまでやる…。どんなラスとかは、上映で確認していただきたい。映画を撮ることの喜びと苦悩を12分の断片的なシーンで描いたこの作品は、見事、PFFアワード1984で入選した。私も同じ年に作品を応募したが、落選してしまった。しかし、この作品に協力出来たことは良かったと思う。ちなみにオープニングにかかっている音楽は、私が提供した〝財団法人じゃがたら〟のシングル盤のB面に収録されている「ヘイ・セイ」である。
『過去形という魚』は私が大学を卒業して実家のある浜松で就職していた時期に撮った作品だ。23〜24歳だった。「イメージ・マーケット」に顔を出したりバンドを組んだりもしていたが、地方都市の閉塞感や会社勤めの馴染めなさに、鬱々とした日々を送っていた。東京で上映会を開くことになり、日記映画を取ろうと思ったが、自分には語るべきものごとがない気がした。自分には何も特別なものはない…。とりあえず家族にカメラを向けてみることにしたが、両親や妹たちを撮っても何も起こらない。しかし、祖母にカメラを向けると、彼女は突然自分の死装束が用意してあるということについて話し出した。それは小さな奇跡だった。自分の家族が撮れなかった私は、他人の家族を撮ろうと思った。友人のN君に協力してもらい、彼の家族を彼に撮ってもらうことにした。彼の家族を鏡にして、自分の家族について考えたかったのだ。多分、私は自分を面白いと思っていなかったのだ。だから、私は自分のことをなるべく赤裸々に語らなくてはならないと考えていた。恥ずかしい本音をさらけ出せば少しは面白くなるかも知れない。そう考えながら、何も出来ない自分がもどかしかった。つまらない日常、つまらない自分、この映画にはそうした当時の気分が詰まっている。そして、今でもその考えにそんなに変わりはない気がする。ただ、30年以上という時間の経過は色々なものを変えてしまった。祖母や父親をはじめ、亡くなってしまった人たちも多い。N君は消息不明になってしまった。この作品は当初ライフワークとして撮影を続け、新たに編集してゆくという予定だった。祖母の亡くなった時も私はカメラを回した。しかし、結局それらは作品に加えられることはなかった。公開当時全く無視されてしまったこの作品が今、どのように受け止められるのか楽しみだ。